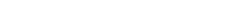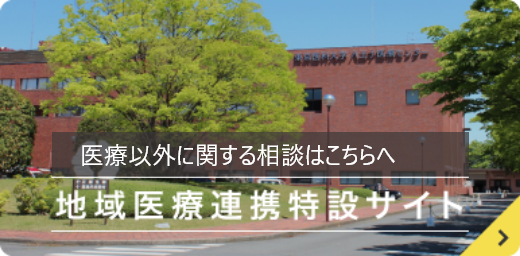重要なお知らせ
Important News
お知らせ一覧
※ラベルをクリックするとカテゴリー毎のニュースがご覧いただけます
-
2025.05.08
-
2025.12.15
-
2025.12.15
-
2025.11.28
-
2025.11.05
-
2025.10.06
-
2025.10.01
-
2025.09.30
-
2025.09.17
-
2025.09.17
-
2025.07.09